エンジンとは?
エンジンとは、燃料を燃焼や爆発によって、生まれる膨張圧力を動力に変換する機関の総称で、蒸気機関など外からの熱でエンジン内部に蒸気を発生させるものを外燃機関。エンジン内部で、燃料を爆発させて直接その圧力を動力に変換するものを内燃機関と呼びます。一般自動車に使用するエンジンは、内燃機関で、揮発性の高いガソリンなどの液体を空気と混合して気化したものをエンジン内部に噴射し圧縮した状態で着火し爆発をおこし、その爆発力によって、ピストンを押し下げる力でクランクシャフトを廻し、動力に変換します。
エンジンの種類
自動車に使われるエンジンの構造は、大半がレシプロエンジンでマツダ車の一部でロータリーエンジンが使用されています。また、燃料によって、ガソリンエンジン、軽油を燃料とするディーゼルエンジン、LPガスを燃料とするLPガスエンジンなどに分けることもできます。レシプロエンジンについては、シリンダー(気筒)の数や配置によって、V型6気筒エンジン、直列3気筒エンジン、水平対向4気筒エンジンなどに種類分けすることもできます。
エンジンの仕組
自動車に使われる一般的なエンジンは、燃料を問わず、吸気、圧縮、爆発、排気の4つの行程を繰り返し、動力に変換しています。
一般的なガソリンエンジンの行程
| 1.吸気 | 空気と混合した燃料をエンジンシリンダー内に吸気 |
| 2.圧縮 | エンジンシリンダー内で空気と混合した燃料を圧縮 |
| 3.爆発・燃焼 | 圧縮された燃料に着火。爆発による膨張でエンジン外部への動力に変換する |
| 4.排気 | 燃焼後の排ガスをエンジンの外へ排出 |
レシプロエンジンの仕組
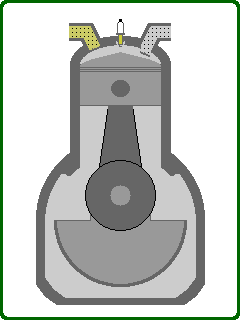 レシプロエンジンは一般的な自動車に使用されているエンジンで、4サイクルエンジンを例に解説すると、その仕組みは、シリンダー(筒)内に空気と混合した、燃料を噴射し、ピストンの押上により燃料が混ざった気体が圧縮されます。ピストンが上がり切った(圧縮された)ところで、爆発させ、爆発による膨張力でピストンを押し下げ、ピストンが下がり切った時に排気弁が開き、ピストンの押し上げにより、排気ガスが押し出される。この行程を繰り返し、燃料の爆発によるピストンの上下運動を、クランクシャフトによって、回転運動へと変換する。クランクシャフトを軸にV型や直列などにシリンダーを連接し、行程のタイミングをずすことによって、滑らかな回転が得られる。4サイクルエンジンの場合、吸気、圧縮、爆発、排気の4つの行程で、ピストンは、2往復し、クランクシャフトは、2回転する。
レシプロエンジンは一般的な自動車に使用されているエンジンで、4サイクルエンジンを例に解説すると、その仕組みは、シリンダー(筒)内に空気と混合した、燃料を噴射し、ピストンの押上により燃料が混ざった気体が圧縮されます。ピストンが上がり切った(圧縮された)ところで、爆発させ、爆発による膨張力でピストンを押し下げ、ピストンが下がり切った時に排気弁が開き、ピストンの押し上げにより、排気ガスが押し出される。この行程を繰り返し、燃料の爆発によるピストンの上下運動を、クランクシャフトによって、回転運動へと変換する。クランクシャフトを軸にV型や直列などにシリンダーを連接し、行程のタイミングをずすことによって、滑らかな回転が得られる。4サイクルエンジンの場合、吸気、圧縮、爆発、排気の4つの行程で、ピストンは、2往復し、クランクシャフトは、2回転する。ロータリーエンジンの仕組
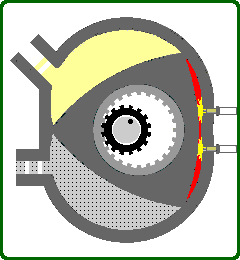 ロータリーエンジンは、レシプロエンジンと同様に、吸気、圧縮、爆発、排気の4つの行程の繰り返しで、動力を生み出しますが、ピストンを使用せず、ぺリトコロイド曲線という特殊な形状をしたシリンダー(ローターハウジング)内に三角形に似たローターを配しています。ローターハウジングとローターとの間に出来た3つの隙間で吸気、圧縮、爆発、排気を同時に繰り返し、ローターに偏芯で(芯をずらして)取り付けられたエキセントリックシャフトを介し回転運動を伝達しています。ローターが1回転するとエキセントリックシャフトは、3回転します。
ロータリーエンジンは、レシプロエンジンと同様に、吸気、圧縮、爆発、排気の4つの行程の繰り返しで、動力を生み出しますが、ピストンを使用せず、ぺリトコロイド曲線という特殊な形状をしたシリンダー(ローターハウジング)内に三角形に似たローターを配しています。ローターハウジングとローターとの間に出来た3つの隙間で吸気、圧縮、爆発、排気を同時に繰り返し、ローターに偏芯で(芯をずらして)取り付けられたエキセントリックシャフトを介し回転運動を伝達しています。ローターが1回転するとエキセントリックシャフトは、3回転します。ディーゼルエンジン
日本では、その経済性から貨物車に多く用いられるディーゼルエンジンですが、ガソリンエンジンとの違いは、燃料に揮発性の低い軽油を使用するということ。(自動車以外に使用するエンジンの場合は、重油などを使用するものもある)その為、エンジンの構造もガソリンエンジンと若干、異なり、ディーゼルエンジンの場合は、スパークプラグを使用せず、ガソリンエンジンの場合の吸気行程では、空気だけを吸入圧縮し、エンジンシリンダー内で、その熱せられた圧縮空気に直接、高圧の燃料を吹き込むことによって、爆発・燃焼を起こすというもので、シリンダー内に燃料を注入するタイミングがガソリンエンジンのそれと異なる。
エンジンの排気量
エンジンの大きさを示す為に用いられるのが排気量で、これは、レシプロエンジンの場合、ピストンが下死点にあるときのシリンダー内の容積から、上死点にあるときの容積を差し引いた容積をいいます。つまり、エンジンシリンダーの吸気から排気という1回の行程で排出される排ガスの容量を表したもので、この数値にエンジンを構成しているシリンダーの数を乗じたものを総排気量という。

 Cars Japan Top
Cars Japan Top